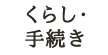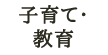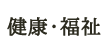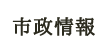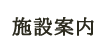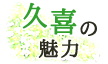第155回 栗橋銀行と栗橋商業銀行
更新日:2024年12月12日
問い合わせ先:文化振興課文化財・歴史資料係
明治26年(1893)7月の銀行条例制定と日清戦争後の諸産業の発展に伴い、明治20年代末から普通銀行が急増しました。その一つが栗橋銀行です。明治31年7月、栗橋銀行は地元の期待を担って開業しました。創立時の頭取は吉岡竹三郎(よしおかたけさぶろう)、取締役は遠藤(えんどう)たん吉(きち)(注釈)等が名を連ねています。栗橋銀行が設置された場所は、陸羽(りくう)街道(旧日光道中)沿い西側で、加須町(現加須市)に至る農道との角地付近でした。設立当初の資本金は5万円(1株50円 1000株)で、開業の翌年12月には、加須町に支店を設けています。明治34年6月には、資本金15万円に増資しました。
一方、栗橋銀行とは別に栗橋商業銀行もありました。栗橋商業銀行は、明治33年8月、栗橋町に資本金3万円で、場所は陸羽街道北側の八坂神社と旧関所跡との中間付近に開業しました。同行は明治42年、入間郡南古谷村古市場(現川越市)の豪商橋本三九郎(はしもとさんくろう)に買収されて同村に移り橋本銀行と改称しましたが、業績悪化により昭和7年(1932)に解散しました。
このような地元資本による地元産業に密着した弱小銀行は、それぞれ厳しい経営環境にありました。加えて、第一次世界大戦によってもたらされた空前の好況は、大正9年(1920)3月に至り、反動恐慌へと転じました。大正11年9月、栗橋銀行は倍額増資して資本金を30万円としましたが、反動恐慌による不況がまだ回復しない中、大正12年9月1日に関東大地震が起こり、加須支店の休業を余儀なくされるなど苦境に立たされました。ちょうどその頃、経営基盤の強化を図るために銀行間の合併の動きがあり、栗橋銀行は、大正15年12月に忍(おし)商業銀行に合併されました。
忍商業銀行は、第二次世界大戦の戦局が悪化する中、大蔵省の勧奨により、昭和18年(1943)武州銀行、第八十五銀行、飯能銀行と合併、同年7月1日に「埼玉銀行」として新たに開業しました。この埼玉銀行は、現在の「埼玉りそな銀行」となっています。
※注釈
「たん吉」の「たん」の字は以下の通りです。


栗橋銀行の額
このページに関するお問い合わせ
教育部 文化振興課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:bunka@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する