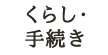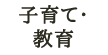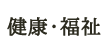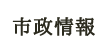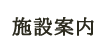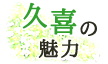第156回 久喜市の十九夜塔と女性たち
更新日:2024年12月12日
問い合わせ先:文化振興課文化財・歴史資料係
寺社の境内あるいは道沿いに、「十九夜」など、「○○夜」と刻まれた石塔(せきとう)を見かけることがあります。これらは月待(つきまち)塔と呼ばれ、月待行事を記念して造られたものです。月待とは、十八夜や十九夜、二十三夜など、特定の月齢(げつれい)の日に複数人が集まり、共に飲食をしながら月の出を待つ行事です。その起源は中世にまでさかのぼるとされていますが、江戸時代以降には、人々の集まりの場という側面が強くなりました。月待による集まりは、昭和期まで各地で行われていました。
久喜市内には、月待塔が40基ほど確認されています。造立されたのは主に江戸時代後期で、その半数以上が月待の一種である十九夜信仰を行う組織(講(こう))によるものです。十九夜講は主に女性で構成され、如意輪観音菩薩(にょいりんかんのんぼさつ)を本尊として祀り、安産やこどもの成長を祈願します。江戸時代に栃木県や埼玉県などの関東や東北地方に広まり、久喜市内では特に栗橋地域や鷲宮地域に多く見られます。
十九夜講は参加した女性にとって、単なる信仰の場以上の意味合いがあったようです。平成2年(1990)から翌年にかけて旧栗橋町で実施した調査によると、北広島地区では毎年3回、19日に女性たちがこどもを連れて昼頃から集まり、如意輪観音の掛け軸の前に供え物をし、無病息災を祈願して会食したといいます。その場に男性が入ることはいっさい許されず、女性は情報交換を行うなど親睦を深めていました。参加者の話では、娯楽がない中でその日はとても楽しみであったそうです。
十九夜講は、命がけの出産やこどもの成長に対する女性の不安を取り除くとともに、女性が周囲を気にすることなく心身ともに休まるために重要な場であったといえます。

北広島地区の十九夜塔
このページに関するお問い合わせ
教育部 文化振興課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:bunka@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する